
千組千曲選テーマ別まとめ第六弾は、1970年代にヒットした名曲を22曲紹介します。
チョイスした千組を眺めているとポピュラーなヒット曲もそれなりに存在しているので、これなら1年毎のヒット曲選出をやれるのではないかと思い、選出してみました。年によって選曲数に差があるのは企画の性質上お許し下さい。
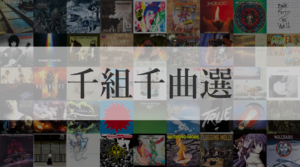
1970年の名曲
Mashmakhan / As The Years Go By
邦題は“霧の中の二人”。本国カナダとアメリカでスマッシュヒットした後、1971年の1月には日本でオリコンチャート1位を記録する大ヒットとなった曲です。
いかにも日本受けしそうな哀愁と熱情が交差するポップロックサウンドはもちろん私も大好物。実際はプログレ的なロックバンドでこの一曲のみが世代を超えて愛され続けているわけですが、それだけの力ある楽曲です。
Shocking Blue / Never Marry A Railroadman
邦題は“悲しき鉄道員”。なんと原曲から回転数を上げたことで(テンポが速くなるだけでなくピッチも上がる)日本で大ヒットしたナンバー。これはまあ時代性ですね。
それにしても綺麗な女性に「鉄道員と結婚しちゃダメよ」と言われているから邦題“悲しき鉄道員”という流れは面白いですね。まあ鉄道員は比喩なので、そこまで汲んだら“浮気男にご用心”なんて邦題になりそうで、やっぱりこのままでよかったかな(笑)
Mungo Jerry / In The Summertime
世界で最も売れたシングルのトップ3に名を連ねる、歴史に残る超ヒット曲。しかし心震わせるような感動の曲ではなく、とってもリラクシングな夏の愛されソングです。
彼らはイギリス本国だと他にもヒット曲がありますが、世界的にはこれほどの規模の”One Hit Wonder”な存在は無いでしょう。今年も暑い休日にはダダディディダ~っとこれを聴きながら寝ころびたい・・・
1971年の名曲
Marvin Gaye / What’s Going On
反戦歌としての歴史的な位置付けだけでなく、美しいR&Bの代表として純粋に愛され続ける名曲。同名のアルバムもソウル・ミュージックを代表する名盤として有名です。
発売当時の邦題は“愛のゆくえ”ですが、この作品のタイトルとしてはやはり不正確かなと思いますね。そのまま”どうなっちまってるんだ?”みたいなタイトルの方が日本の世情的にも合った気がします。
John Denver / Take Me Home, Country Roads
邦題は“故郷へかえりたい”ですが、既に”カントリーロード”として有名でしょう。まさにジャンルを超えて愛される名曲です。
デンバーと言えばロック好きにとっては1985年にPMRCの働きかけで行われたアメリカ議会での公聴会において、表現規制反対派として証人出席したことが有名です。ザッパとディー・スナイダーというアクの強い他の証人と音楽面では通じ合えたのでしょうか・・・(いらぬ心配/笑)
加藤和彦と北山修 / あの素晴しい愛をもう一度
1971年の楽曲。日本フォークソング史に残るナンバーで、一過性のヒットというより長く歌い継がれていく名曲となりました。私は小学生の時に音楽の授業で出会い、その時からずっと好きな歌です。
高校時代にギターを弾くようになってからはスリーフィンガーの練習でもお世話になりました。これかKansasの“Dust in the Wind”は定番ですね。
1972年の名曲
Paul Simon / Mother and Child Reunion
邦題は“母と子の絆”。サイモン&ガーファンクル解散後最初のヒット曲で、ジャマイカのミュージシャンによる本格的なレゲエサウンドとポールの詩情が見事にマッチした名曲です。
軽やかなサウンドなのに言葉がすぐには分からない私でもこれは悲しい歌だと初めて聴いた時に感じました。歌詞は様々な背景と解釈があり、S&G時代と同じく色々と考えさせてくれるアーティストです。まあ普段はそこまで深く考えずに心地よさに身を委ねますが(笑)
1973年の名曲
Roberta Flack / Killing Me Softly With His Song
邦題は“やさしく歌って”。時代を超えて愛されるスタンダードナンバーの一つです。Killなんて言葉が出てくるのでギョッとしますが、苦しい恋の胸の内的な内容の詞もおしゃれな印象を増しています。
この歌もネット社会になって初めてカバーであると知った曲で、オリジナルはロリ・リーバーマンによるものとのこと。ロバータが飛行機で偶然聴くことが無かったら、と考えると世の中の面白さを感じますね。
Carpenters / Yesterday Once More
アルバムNow & Thenの”Then”を表したコンセプトナンバーで、古き良きを懐かしむ詞曲とカレンの歌声が胸にしみる名曲です。特に日本で人気が高く、オリコン洋楽チャートで26週連続1位を記録しました。
カーペンターズはリチャードの拘りゆえかアレンジの巧みさと共に録音にも非常に気を使ったものが多く、オーディオ愛好家への誘いとしても存在感があります。私が初めて購入したハイレゾ音源も、実は彼らのSinglesでした。
井上陽水 / 氷の世界
孤独感を感じさせる独特な詞世界がファンキーな曲調で勢いよく飛び出してくる名曲です。この曲が収録された同名アルバムは1975年には日本初のLP売上100万枚を記録しました。
御本人を見る機会よりもものまねを見る機会の方が多く、ものまね番組を観るたび、今の若い人たちに通じるのだろうかといらぬ心配をしてしまいます(笑)
1974年の名曲
Suzi Quatro / The Wild One
世代的には「たけしのお笑いウルトラ・クイズ」エンディングでお馴染み、スージーのまさにワイルドな歌唱とノリのよいロックンロールが気持ち良いナンバー。出身国であるアメリカではあまり支持されませんでしたが、イギリスやヨーロッパでは一定の成功を収めました。
1987年にはBOØWYが発表したカバー(シングル“Marionette”のカップリング)でご本人共演されています。スージーの声から粗野な感じが失われているのは少し残念ですが、演奏含めてそちらも結構好きなカバーです。
Electric Light Orchestra / Can’t Get It Out Of My Head
邦題は“見果てぬ想い”。ストリングスによる大らかなアレンジで包み込むように奏でられるバラードで、彼らの初期の代表曲となったナンバー。アメリカでは成功を収めた一方、何故かイギリスではインしなかったという不思議なチャートアクションを記録しています。
この後外部オケやシンセ等でより豪華な装飾へと進んでいく彼らの起点となった一曲。
1975年の名曲
Bay City Rollers / Saturday Night
“S-A-T-U-R-D-A-Y Night!”というポップソング史に残るキャッチーな必殺フレーズを持つ、彼らの代表曲。理屈抜きで楽しい気持ちになれるという点で凄いナンバーだと思います。
実は1973年に一度イギリス本国でリリースされたもののヒットせず、ボーカル交代後に改めてリリースされアメリカで火が付いたという経緯を持ちます。時の運というものか、運命の非情さを感じずにいられません・・・まあこの歌聴いていたらそんな感傷吹き飛びますが。
Olivia Newton-John / Have You Never Been Mellow
邦題は“そよ風の誘惑”。少し儚げなオリビアの歌声がマッチした、甘いメロディラインで盛り上がるポップソング。
個人的な思い出として大阪で書店のシステム管理の仕事をやっていた際に、店舗に置いてある端末がDell製だったので企業用サポートへ電話することが多く、その時壮大なこの曲のアレンジを何度も何度も聴かされ続けたことがあります。本来リラックスしなさいというような曲なのに、一時期それでイライラのテーマとなっていました(笑)
太田裕美 / 木綿のハンカチーフ
松本隆さんによるディランの“Boots of Spanish Leather”を日本風にアレンジした詞が印象的な、太田裕美さんの代表曲。筒美京平さんの曲としても個人的に一番好きな名曲です。
ちなみに私は昔からこの歌は悲恋歌と思えず、そりゃ別れて当然だろうと思ってしまう人間なのですが、皆さんどうなんでしょう。だって都会で頑張りながら気に掛けて色々しようとしているのに何でもかんでも否定されたらそりゃねえ・・・
1976年の名曲
ABBA / Knowing Me, Knowing You
彼らの数多ある名曲の中で個人的に最も好きな曲。全盛期のアルバムArrival(1976)収録曲で、3枚目のシングルながら多くの国でヒットを記録しました。サビの掛け合いとタイトルコール後の”ah ha-“が堪りません。
小学生の頃から好きで意味も分からず歌っていましたが、どストレートな離婚の曲と知った時はビックリしました。”アハ~ン”とか言ってる場合じゃねえだろ!と突っ込みたくなる一方、この内容でこのポップさはさすがの一言ですね。
Boston / Peace of Mind
アコギのストロークから爽快に滑り出した後は、ギターやコーラスのオーバーダブをふんだんに用いたサウンドがキャッチーに迫ってくる彼ら印満点の名曲。
完璧主義者と言われたトム・ショルツが作り出したサウンドはその後のポップス/ロック双方へ大きな影響を与えたと思えます。こうしたものを“産業ロック”等と蔑んで嬉しがっているなんて、中学生位には卒業してほしい恥ずかしさですね(毒)
1977年の名曲
Bee Gees / Stayin’ Alive
彼らだけでなくディスコ時代そのものを代表するナンバー。全編ファルセットボーカルという異様さも吹き飛ぶほどのパワーを持った唯一無二の名曲です。
ビージーズ全体としては初期のコーラスグループ然とした時代の方が好み。1990年代はドラマの影響でリバイバルヒットが日本でありましたが、ポップス史に残る巨人としては何となく地味な扱いを受けているように感じます(私だけ?)
Earth, Wind & Fire / Fantasy
こちらもまさにファルセット&ディスコの時代。ダンサブルながら哀愁溢れる、日本において特に支持が厚い名曲で、フィリップ・ベイリーの綺麗な高音と共にモーリス先生の渋いボーカルも聴きものです。
この曲はフォーリーブスによるカバー(1978年)が存在しており、原詞の雰囲気を損なわない日本語詞は結構苦労されただろうなと思わせる力作です。まあ原曲が大ヒットしちゃうとカバーの需要は無いのですが・・・
1978年の名曲
Gloria Gaynor / I WIll Survive
邦題は“恋のサバイバル”。ディスコブーム全盛時代の世界的大ヒット曲ながら、時代や風俗を飛び越えて愛されるようになった自分応援歌の名曲です。ラテン的哀愁とアップテンポなノリが共に歌わずにはいられない力を放っています。
2020年にはコロナウイルスが世界を震撼させる中でこの歌が再び注目されリバイバルヒットを記録しました。個人的にはAJ&クイーン(Netflix, 2020年)における使い方もよかったです。
1979年の名曲
Dschinghis Khan / Dschinghis Khan
西ドイツ(当時)から登場し、ヨーロッパと日本で大ヒットを記録したダンスナンバー。アジアというよりは東欧的なメロディですが耳なじみ良く、何よりジンギスカンとウッ!ハッ!のインパクトが忘れられない名曲です。
現在だとこういう歌やグループは許されないかもしれません(アングラではともかく)。良い曲を残してくれたなあとだけ思っておきましょう。
Blondie / Heart of Glass
ラストもダンスシーンの影響により生まれたこの名曲を。元は1975年に発表している“Once I Had a Love”という楽曲をアレンジしたもので、見事なディスコ調に生まれ変わり世界で大ヒットを記録しました。
ブロンディの中では異端な印象の楽曲ですが、浮遊感漂うアレンジとデボラの器用なボーカルが見事。本人たちにとってはどうだったのかな、と考えてしまいますが。
以上、22曲をご紹介させて頂きました。
終盤は思った以上にディスコ三昧な感じになってしまいましたが、私のアンテナ的にヒット曲はノリのよいものを求めているのかもしれません。
一気にやると疲れるけど、次回は続いて1980年代の予定です。
おまけ
SSランク/Sランクの1970年代ヒット曲
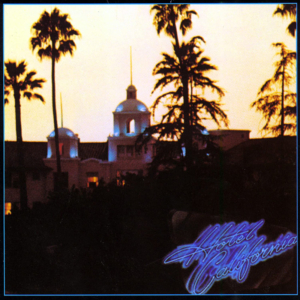
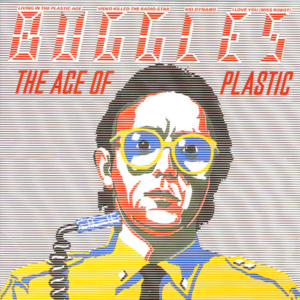
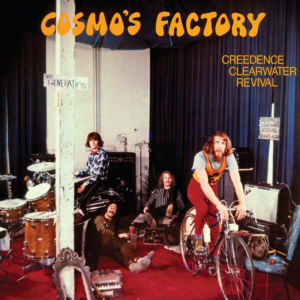
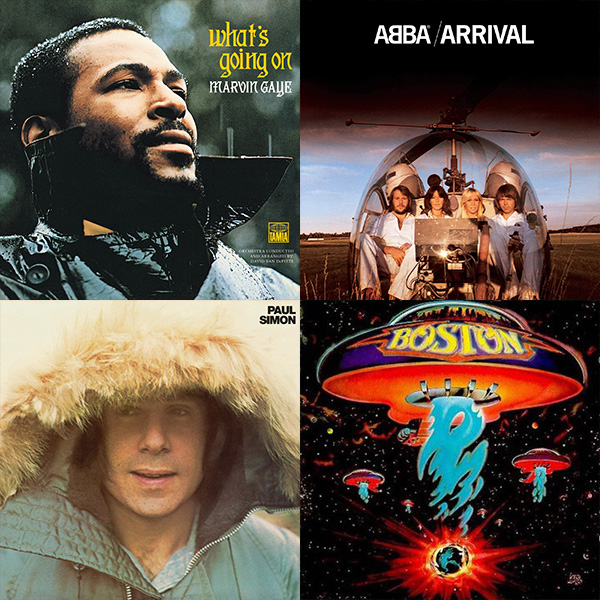






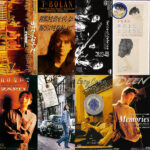

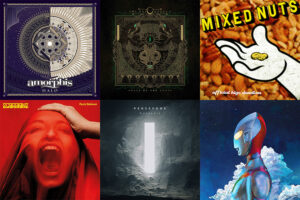

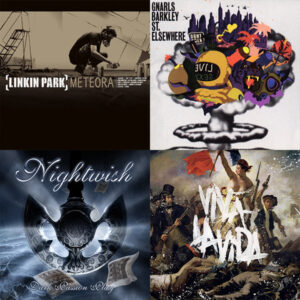


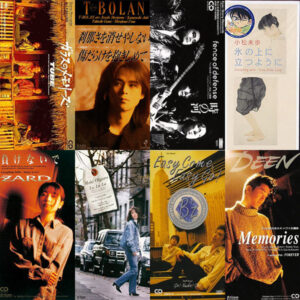


コメント