
千組千曲選テーマ別まとめ第十弾はメロディック・デスメタル(Melodic Death Metal、通称メロデス)の名曲を紹介します。
年代毎のヒット曲まとめを続けていこうと思ったのですがモチベーションが上がらなくなってしまったので、自分が親しみまくったジャンルで仕切り直しとさせて頂きました。2000年代以降のヒット曲は改めて取り上げます。
さて、メロデス。私が青春メタラー真っ盛りだった頃に勃興~発展~隆盛~変容までをがっちり体験したと言えるシーンです。それだけにむしろ主観が入りまくってしまい、一般的な共感を得られない可能性もありますが、あくまで一個人が捉えたメロデスというジャンル範囲における解説と名曲選としてご了承の上、お読み頂ければ幸いです。
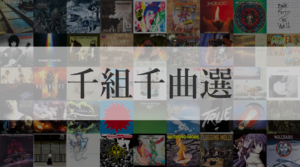
メロデス勃興期の名曲
いつからメロデスが始まったかについて、一般的に定義することは難しいとされています。アメリカで発展したデスメタルの影響が北欧の地に及び、1990年代初頭にいわゆるスウェディッシュ・デスメタルのシーンが形成されますが、スウェーデンのデスメタルバンドは少なからずメロディアスなテイストを持っており、後追いで聴く(=後年の基準で考える)と「これもメロデスやん」というサウンドは既にこの時点でも存在していたからです。
ただ当時はあくまでも「北欧のデスメタル」として受容されており、シーンにおいて、つまりバンド側が明確にメロディアスさを提示し、リスナーもそれを主体に求め始めるのはもう少し後の話。この時代のバンドによるサウンドを“メロデス黎明期”と捉えてもよいと思いますが、私の区分ではデスメタルの方へ含めさせて頂くことにします。(具体的にはEntombedやDismember、Desultoryといったバンドや、初期Edge of Sanity、Amorphisなど)
そんなわけでメロデス元年はやはり1993年。この年発表された楽曲とアルバムから、以下のような要素を併せ持つヘヴィメタルのシーンが生まれ、注目されていくことになります。
- デスボイス(ガテラル)やスラッシュメタル由来の吐き捨てなど、メロディの無いボーカル
- デスメタルやスラッシュメタルの延長線上にある激しいリズムと歪み(=グルーヴメタルとは異なる)
- いわゆる正統派、様式美メタルやフォーク要素を持つドラマティックでメロディアスな旋律の挿入
もっと深く突っ込んでいくと当時のグルーヴやヌーメタルが力を得ているメジャーシーンへのアンチテーゼだったり、ブラックメタルとの過激音楽シーンにおける争いだったり、他者は関係なく単に好みの揺り戻しだったりと色んな時代の要素があるのですが、まあそんな話は専門家の方にまとめて頂くことにして、ここからは企画に戻り勃興期として1993年~1995年頃までの名曲を取り上げていきたいと思います。
SS/Sランクで既に取り上げ済みの名曲~勃興期編
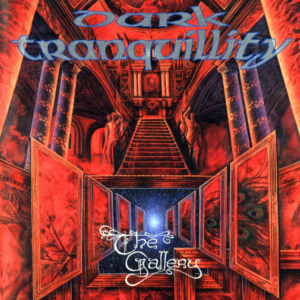
Carcass / Heartwork
1993年の同名アルバムHeartwork収録曲。日本においてはヘンテコな邦題と“リバプールの残虐王”という呼び名、それを物語る悪趣味なジャケットで名を馳せたグラインドコアの雄が、突如ツインリードでドラマティックなメロディをまき散らしてシーンを(ある意味)震撼させた一曲。
今となっては前作から加入したスウェーデン人ギタリスト、マイケル・アモットによるインプット、と言うより彼そのものが出た曲と分かるのですが、当時突然変異としか思えなかったインパクトがシーンに与えた影響は絶大でした。バンドは本来のイメージとのギャップにこの後苦しむことになりますが、メロデスにとっては歴史的な存在感を示し続ける名曲です。
Edge Of Sanity / Darkday
1993年のアルバムThe Spectral Sorrows収録曲。メロデスの始祖の一つとして有力な存在に挙げられるバンドによる、ストレートな疾走感を持つパートと浮遊感のあるパートがメロディアスな旋律で繋げられた、メロデスの一類型を示した先駆的名曲。
彼らはデスメタルをベースに“何でも取り入れていく”という姿勢を示した代表的なバンドでもあり、アルバムを追う毎に変化/進化を見せる姿勢は孤高の精神を感じさせました。一方でそのために学生の少ないお小遣いで挑戦するには冒険的すぎる存在であったため、正直リアルタイムではあまり親しめなかったのも事実です。Crimson(1996年、1曲で1アルバム)を当時聴いてみたかった・・・(魅力に気づかなかったかもだけど)
In Flames / Stand Ablaze
1994年のミニアルバムSubterranean収録曲。日本において長らくメロデスにおける名曲として絶対的な地位にあった曲。BURRN!誌編集者前田岳彦氏(当時メロデス分野発掘における第一人者という印象)による猛プッシュの影響もあり、あの時代にメロデス愛好家でこの曲を聴いていない人は日本に存在しなかったのではないでしょうか。音質や曲展開の強引さ等を不満に感じる声もあるようですが、それらも含めて時代の空気感を濃厚に伝える歴史的な名曲として、当時のある意味余計な思い入れが無い方にもおすすめできます。
彼らの発表作品はそれそのものがメロデスの歴史のような重要作/名作/問題作(良い意味でも)が多数ありますので、メロデス初心者の方には入門バンドとして時代を追って聴かれることもおすすめします。その場合は必ず1990年代から入られますように・・・
Sentenced / The War Ain’t Over!
1995年のアルバムAmok収録曲。スウェーデンと並ぶメロデス重要国フィンランドの初期シーンを代表するバンドの一つによる、ドラマティックなギターリフが冴え渡る名曲。ミーカ・テンクラの粘っこいリードギターは私の好みにどストライクで、アルバム自体もメロデス勃興期屈指の名盤として愛聴してきました。
その後の彼らは独自のメランコリックメタルを創出し名作を発表しますが、あくまで個人的な好みではこの時代の魅力を超えることはありませんでした。演奏面の危なっかしさや強引な展開等の粗削りさが逆説的に生み出すスリリングさと、後のメランコリックメタルにも通じる不思議な浮遊感の芽生えなど、この時代にしかない魅力を是非味わってほしいと思います。
At The Gates / Blinded by Fear
1995年のアルバムSlaughter of the Soul収録曲。スラッシュメタル寄りのメロデスを語る上で避けて通れないバンドによる問答無用の一曲。SEとナレーション後に爆発するようなテンションで奏でられるリフはメロデス史に残る名リフです。
この後のシーン隆盛期には解散分裂してしまっており、日本では重要バンドの地位から脱落してしまいましたが、後にアメリカにおいて形成されたメタルコアシーンへの影響とそのルーツ評価により、世界的には最も権威あるメロデスバンドとして評価されるようになりました。再結成後はメンバー変更がありながらも順調に活動を続け、来日も何回か実現しています。
メロデス隆盛期の名曲
1996年頃には一定のファン層も出来上がり、様々な呼び方をされていたシーン(叙情派デス、耽美派デス等)がメロディック・デスメタルシーンとしてメタラーに共通認識されるようになります。地下メタル的存在からの脱却を示すようにバンドロゴが普通に読めるようなデザインに変わる(In Flamesやamorphis)など、バンド側もよりメジャーを意識するようになり、作品も音質や展開などが洗練されていくようになりました。
1997年にArch EnemyがCathedralのサポートアクトながら初来日で熱狂的に歓迎された後、1998年にはIn Flamesが川崎クラブチッタの観客動員記録を塗り替える等、メロデスはシーンの中心である北欧から遠く離れた日本においても“今最も熱いメタル”として大きな支持を得ました。
1999年7月8日、今はなき梅田ヒートビートで観たChildren of Bodom/Sinergy/In Flamesのライブはこの時代の個人的クライマックスとして忘れられない思い出です。チルボドの印象が凄すぎてあとの2組の記憶はほぼ飛んでしまいましたが(老化)
一方で先駆者であったバンドの中にはデスメタル要素を排除する動きも出てきます(amorphisやSentencedなど)。彼らの変化はかなり大胆なものであったため、基本的にはメロデスの幅を広げることは無く、メロデスという枠から“出ていった”と見なされておりました。メロデスシーンが本格的な変容を迎えるのはもう少し後の話です。
というわけで1996年頃~2000年頃までの名曲を挙げていきます。
SS/Sランクで既に取り上げ済みの名曲~隆盛期編

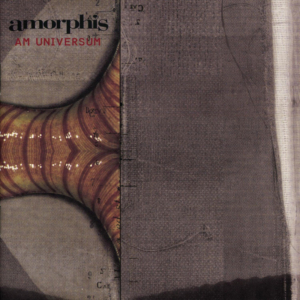
Arch Enemy / The Immortal
1999年のアルバムBurning Bridges収録曲。当時からファンである自分は未だにアーク・エネミーと呼びそうになる、メロデスシーン形成に多大な影響を及ぼしたマイケル・アモット率いるバンドによるキャッチーなメロデスを具現化した名曲。クリストファー・アモットの速弾き~チョーキング~馬嘶きアームプレイソロは何度エアギターしたか分かりません(弾けないから/恥)
彼らもIn Flamesと同じく発表作品がそのままメロデスの歴史となるような存在です。個人的にはどうしても1990年代の作品への思い入れが強いですが、世界的なバンドとなってからの彼らも当然おすすめです。好きな曲がありすぎるがゆえに絞りきれず、Sランク認定から外れてしまっていたのは内緒・・・
Armageddon / Funeral in Space
1997年のアルバムCrossing the Rubicon収録曲。クリストファー・アモットが当時サイドプロジェクト的に結成、リリースしたアルバムからの一曲。この曲は全くデスメタル要素の無いフォーキーなインストナンバーですが、北欧メロデスの肝である“慟哭レベルの泣きメロ”が乱舞する愛好家悶絶の名曲です。
バンド自体はその性格上クリストファーのその時々の嗜好に左右され、音楽性も活動も安定しない存在でしたが、この1stアルバムはメロデス勃興期の香りを強く残す名盤としておすすめです。クリストファーは現在Dark Tranquillityに在籍しており、次作での活躍に期待が掛かります(昨今のメロデス回帰ブームが届けば・・・!?)
Embraced / Memento of Emotions
1998年のアルバムAmorous Anathema収録曲。プログレッシブメタルを思わせる複雑な展開と、ピアノが先導するゴシックメタル的な耽美性も孕んだ美しいメロディが激情を煽る個性的な名曲。プロフィールではブラックメタルとされているようですが、サウンド的にはメロデスの文脈にあるバンドだと思います。
よりプログレッシブな展開を盛り込んだ2ndアルバムも意欲的でしたがその後は音沙汰が無く。メジャーフィールドにはなりにくい音楽性であるものの、残された2作品は非常に高品質ですので、手に入る機会があればおすすめしたいと思います。(どこかで再発されればよいのですが)
Ebony Tears / Harvester of Pain
1999年のアルバムA Handful of Nothing収録曲。At The Gates直系のメロデス~デスラッシュスタイルの名曲。この曲収録の2ndアルバム自体名作でしたが、1stアルバムが初期のIn Flamesの叙情性やDark Tranquillityの耽美性を彷彿とさせるサウンドであったために、その延長線上のサウンドを期待したファンからの評価を得られず、その後さらにスラッシュ寄りとなったアルバムを発表した後に解散してしまいました。
後発バンドの中でもかなりのクオリティを誇ったバンドだっただけに残念な流れでしたが、シーンが飽和状態になった中ではよくある光景です。諸行無常なり・・・。せめてメロデス探究者には忘れられないよう、1stと共に評価して頂ければと思います。
Kalmah / Evil in You
2000年のアルバムSwamplord収録曲。前身バンドで長らく苦境を経験し、満を持して2000年にデビューを果たしたフィンランド産メロデスバンドによる1stアルバムの1曲目。問答無用の突進リズムから絶叫にトレモロブラストと、いつ聴いてもイントロからテンションMaxにさせられる名曲です。
前2バンドのその後は寂しい気分になりましたが、彼らはこの後も一貫してストレートに激しく叙情性を忘れない王道メロデススタイルを維持、根強い支持を集めながら活動を続けております。創作ペースは段々落ちてきている感がありますが、今年(2023年)5月に予定されている新作も変わらず期待!
Demoniac / The Eagle Spreads Its Wings
1999年のアルバムThe Fire and the Wind収録曲。当時メロデスにおける“メロ”を突き詰めた存在として話題となった問題作の代表曲。“ボーカルがデスボイスでなければ普通のメタル”と揶揄されることもあったメロデスをその通り具現化した究極の姿。ここまで行くとメロデスどころかメタルですらなくメロコアみたい、と思ったのは昔の私の感想です。今となってはDragonforceの前身として有名なので当時ほどの衝撃は無いと思います(それでも十分初見インパクトはありそうですが)。
忘れられない思い出話として、当時これを聴いて「未来のメタルを担うのはこいつらじゃないか?」と言った非メタラーのY君(ベーシスト)は凄い卓見だったなあと後ほど感動しました。私はネタとして聴かせたつもりだったのにw
メロデス変容期以降の名曲
2000年代に入ると日本と北欧のみの盛り上がりだったシーンに変化が生まれました。アメリカでShadows FallやKillswitch Engageといったバンドがハードコアパンクにメロデスの影響であるツインリード等を取り入れメタルコアのシーンを形成すると、メロデスシーンで先達となっていたIn FlamesやArch Enemyなども逆影響を消化して、北欧的なメロディやデスメタル的な暗さを薄めてグルーヴ感を強めたストレートな曲展開で、世界へ打って出るようになりました。
あくまで個人的な見解ですが、2002年にSoilworkが発表したNatural Born Chaosこそがその後のメロデスシーンの流れを決定づけた作品だと思います。この作品以前からシーンに徐々に表れてきた“変容していくメロデス”の要素が、この作品によって完成形として提示されたと感じたからです。具体的には以下。
- メロディの無いボーカルを基本線としながら、コーラスやブリッジでは歌い上げるパートを導入
- グルーヴメタル的なうねるリフや電子的なエフェクトの導入
- 土着的な要素を排し、明快で分かりやすい展開と旋律(過剰なギターソロの排除も含む)
もちろん全てのバンドが同じようになったわけではありませんが、2000年代に台頭していったバンドたちは多かれ少なかれ似たようなスタイルに集約されていったと感じました。これはつまり私の方が「もう自分が追いかけていく時代は終わったんだな」と認識したということです(これらの変化を好意的に受け止められなくなってしまったため)。
この後の時代についてはシーンをど真ん中で体験している世代ではなくなりましたので多くを語りません。ただ古き良きハードロックや正統派ヘヴィメタルスタイルでも新たな名曲が生まれているように、オールドスクールでも、完成された形でも、変容したものでも、あらゆるメロデススタイルで新たな名曲は生まれ続けています。
ここからはそんなシーンの傍観者となった人間が選ぶ、その後の名曲を取り上げていきます。
SS/Sランクで既に取り上げ済みの名曲~変容期以降編
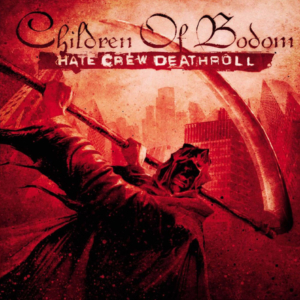
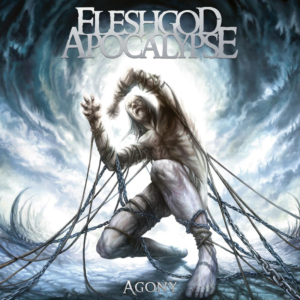
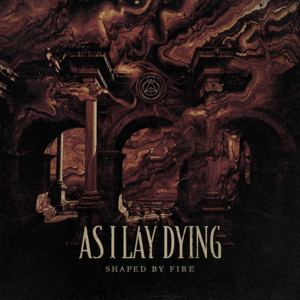
Soilwork / Follow the Hollow
2002年のアルバムNatural Born Chaos収録曲。それまでArch Enemyのフォロワー的な位置付けだったバンドが、大胆なモダン(当時)テイストを取り込んで時代の最先端に躍り出たアルバムの冒頭を飾る名曲。グルーヴィながら猛烈な突進力があるリフと、ここぞと盛り上げるクリーンボーカルの入れ方の巧みさは、まさに新時代の幕開けでした。
トップバンドとなってからも変化を厭わずエクストリームメタルとされる分野の先達的活躍をしておりましたが、流石に私の嗜好的には付いていけない存在でした。でも近年の作風は一周回って面白いものがあるので、もしかしたらこれからまだハマる作品が出てくるかもしれないと期待しています。
Disarmonia Mundi / Common State of Inner Violence
2004年のアルバムFragments of D-Generation収録曲。ほぼ“一人でバンド”エットレ・リゴッティを中心としたイタリアのバンドによる2ndアルバムの冒頭曲。Soilworkのビョーンがボーカルとして参加したこともあってか完全にその系譜のサウンドでありつつ、本家をも上回るスリリングさで喝采を浴びた名曲です。電子的なエフェクトが非常に効果的な形で導入されたスタイルには大きな衝撃を受けました。
この作品の完成度があまりにも高かったためにその後の作品はやや焼き直しっぽい印象を受けてしまいましたが、一時代を築いたバンドだけに未経験の方にはどの作品も問答無用でおすすめします。ここ数年は活動が見られないようで少し心配です。。
Non Human Level / Divine Creation of Void
2005年のアルバムNon Human Level収録曲。Darkaneで活動しているギタリストであるクリストファー・マルマストロームが、メインバンドに合わないと感じた楽曲を発表するために作ったサイドプロジェクトバンドによる一曲。そしてそれがメインバンドのどの曲よりも素晴らしいという・・・ゴホンゴホン。
美しいながらも不穏さを感じさせるアルペジオによるイントロ、ねっとり感のあるリード、スラッシュ由来のキビキビとしたリフ。音作りは洗練されておりますが、要素はまさに昔ながらのメロデスで大好物。アルバムの出来も大変素晴らしく、この後の活動が無いのが残念なバンドです。
Dark Lunacy / Aurora
2006年のアルバムThe Diarist収録曲。デビュー時はゴシックメタルさながら管弦楽を導入したメランコリックなサウンドで注目を浴びたイタリア出身のバンドが、コーラス+バンドのシンプルなスタイルでレニングラード攻防戦を描いたコンセプトアルバムを制作。前二作よりも激しさを高めつつ、ロシア民謡も取り入れ悲哀感を増した珠玉のメロディが胸にしみる名作となりました。これはそのリーダートラックです。
しかしこの名作発表後メインソングライターだったエノミス氏を始めメンバーが続々脱退、バンドを立て直しリリースされた作品がプロダクションも曲レベルもかなりいまいちな出来で酷評され、一気にファンが離れてしまいました。正直この作品以後は別バンドとした方がよかった気がします。(まあそうはいかないのがビジネスの世界であることはもう理解しておりますが)
Die Apokalyptischen Reiter / Friede sei mit dir
2006年のアルバムRiders on the Storm収録曲。伝統的なヘヴィメタル・メロデス・ブラック等の要素をごちゃ混ぜにぶっ込み、クセの強いドイツ語ボーカルと共にバンドが持つ個性的な魅力を3分間ポップスとして凝縮することに成功した奇跡の名曲。この音楽性でこのキャッチーさは、少々ヘヴィメタルから離れがちだった当時の私に衝撃を与えてくれました。
何でもありの雑食音楽グループであるためメロデス変容の歴史とはあまり関わりがありませんが、アヴァンギャルド手前の実験性で楽しませてくれる存在としてカルト的な人気を誇るバンドです。明らかにおふざけもあるけど、それもまた魅力。
Bibleblack / Bleed
2009年のアルバムThe Black Swan Epilogue収録曲。Memento Moriやキング・ダイアモンドとの活動で知られていたマイク・ウィードを中心に結成されたバンドによる、高いクオリティでマニアに称賛を浴びたデビューアルバム内の一曲。流麗なツインリードが散りばめられたメロディック・デスラッシュの名曲として輝きを放っています。
硬派な味わいのデスラッシュバンドとしてその後の活躍も期待したのですが、残念ながら一作品のみの発表で活動は終了してしまったようです。プログレ・メタル風味もあるアルバムは今聴いてもかなりのクオリティを誇るため、甘々なメロデスでは物足りない方は是非。
Destrage / Jade’s Place
2010年のアルバムThe King Is Fat’n’Old収録曲。メロデスにメタルコアにヌーメタルにインダストリアルと、うるさくて気持ちよいものはどんどん取り込んじゃえ!という姿勢がかえって潔いイタリア産ミクスチャーバンドによる代表曲。曲の完成度もさることながら、メタルバンドとしては珍しく見る目にも楽しいPVが話題となりました。
こんなジャンル分け名曲選をしておいてなんですが、この手のバンドを聴くたびに「もうジャンルなんてどうでもいいや」と思えてきます(笑)。古きメタラーの方には自身の許容範囲を知るためのバンドとして、いかがでしょうか。
Omnium Gatherum / Ego
2011年のアルバムNew World Shadows収録曲。フィンランド・メロデス第三世代(なんてものがあるか知りませんが、変容期後にあたる21世紀前半デビュー組)の中でも、愚直なまでに理想のメロデスサウンドを希求し続けるバンドによる一曲。ギターリフ/ハーモニー/オブリがどれを取っても「これぞメロデス!」な哀愁をまとっており、深いデスボイスと相まって私の心に深く刺さった名曲です。個人的に東日本大震災でこれからどうなるのかと不安を抱えた時期にヘヴィローテーションした曲で、あの時の記憶も相まって特別な思いがあります。
バンド自体はこの後も期待を裏切らない作品を作り続けており、現在でも素直に新作が期待できるメロデスバンドの一つです。でも日本では他の第三世代と同じく扱いがマイナー続きな感があるのですが・・・隅っこのおっさんが気にすることではないか。
Insomnium / Lay the Ghost to Rest
2011年のアルバムOne for Sorrow収録曲。フィンランド・メロデス第三世代の出世頭による、ミドルテンポで哀愁を撒き散らす旋律がメタラーの涙腺を破壊してくる名曲。先達であるSentencedのメランコリックメタルやポストブラックにも通じる雰囲気があり、メロデスとしては過激さが物足りない向きもありますが、このメロの前に批判は無力になるしかありません。
Edge of SanityさながらWinter’s Gateという1曲で1アルバムもリリースしており、しかもそんな極端な作品でもフィンランドではナショナルチャート1位を獲得するという、現代メロデスを語る上で避けて通れない存在。ただ個人的にはもう少しストレートに激しいバンドの方がこのジャンルでは愛好するかなー、という気持ちも。最後に下げてしまった(汗)
Mors Principium Est / Leader of the Titans
2014年のアルバムDawn of the 5th Era収録曲。いかにもSoilwork以降といった感があるモダン風味の突進リフを武器に、フィンランド・メロデス第三世代の中でも特に激しく劇的な音楽を作り続けているバンドによるドラマティックな一曲。咆哮もブラストビートもギターソロも絶妙なバランスで素晴らしい。ベースのリフは意外とオーソドックスなメロデス感が強いのもポイントです。
メインソングライターであったギタリストがバンドを去るという事態を、新たな才能を迎えて乗り切ったどころか更に飛躍までしたバンドなのですが、その後またメインソングライターが脱退する(しかも結構な形で)という事態を迎えて昔のギタリストが戻ってきたという展開がここ最近の動向。なんか色々と面倒そうですが、初期テイストの復活は次回期待してもよいかもと新作を待っています。
最後に
メロデスの名曲として21曲(+Sクラス以上6曲)を紹介しました。千組千曲選のルールにより同じバンドの他の名曲/重要曲が紹介できなくてメロデス総括としてはやや消化不良感がありますが、まあ企画のうちなのでこんなもので。ルール関係なくやると三桁以上曲を引っ張ってきて誰も付いてこなくなりそうだし・・・
やはりジャンルを特定して書く方がテンションを保ちやすいので、またぼちぼちと千組千曲選完成までこの形式で続けていきたいと思います。



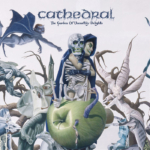
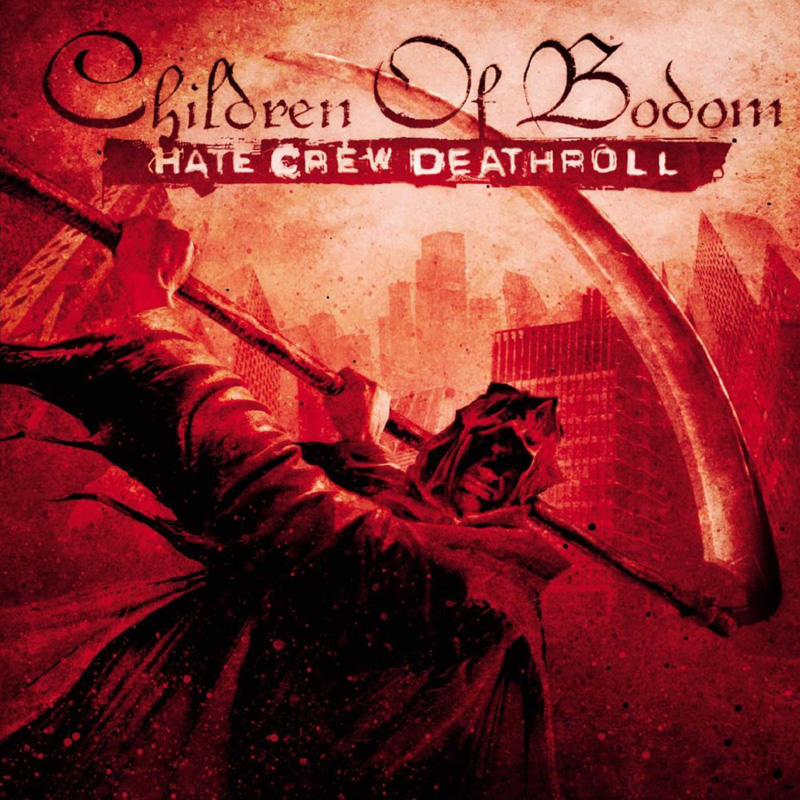
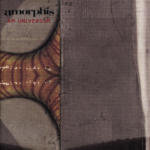
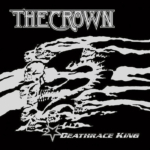
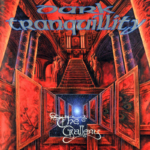
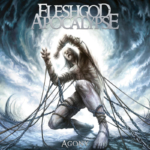

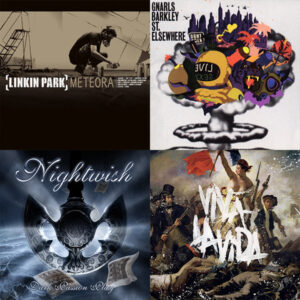



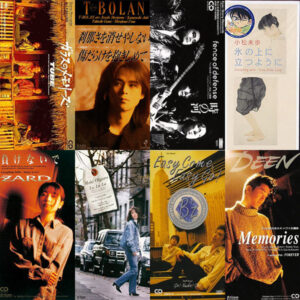


コメント